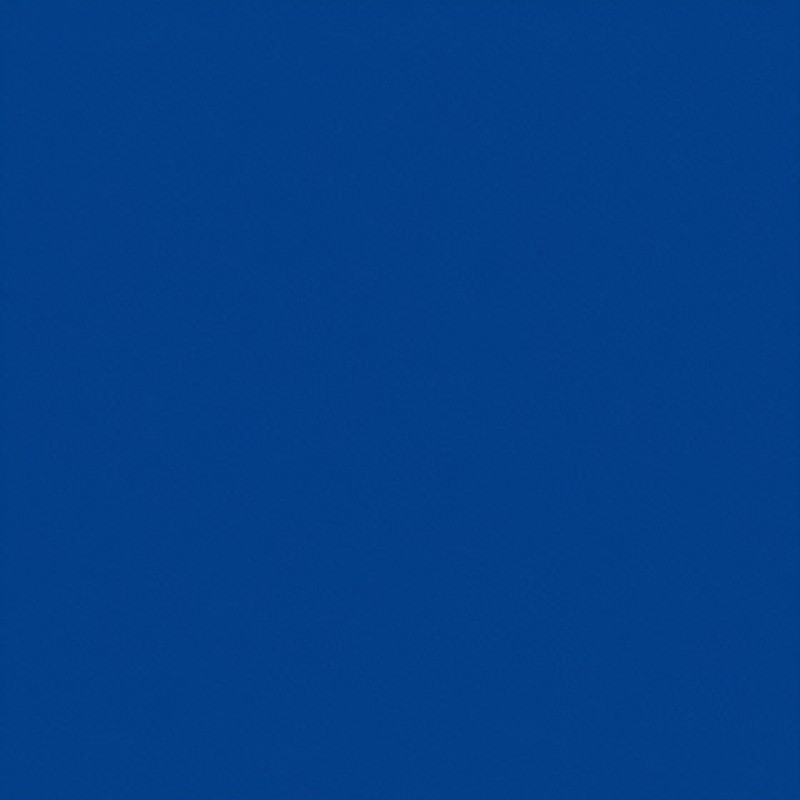うちの子供忘れ物が多くて…?どうしたら忘れ物をしなくなる?
そんなお悩みを抱えるお母さん・お父さん必見!この記事では教育学の視点から「子どもの忘れ物が多い理由」と「叱らずに習慣を身につけさせる具体的な対応法」を3つ紹介します。
1.なぜ子供は忘れ物が多いのか?
①ワーキングメモリがまだ発達段階だから
ワーキングメモリ=情報を一時的に記憶し、それを処理するための脳の機能のこと。
私たちが普段、情報の保持や情報の処理、注意のコントロールができるのはワーキングメモリのおかげです。大人でもワーキングメモリが強い人と弱い人が存在します。
しかし子供はまだワーキングメモリが発達段階にあるため、大人に比べて記憶のコントロールが未熟なところがあります。
②注意の分散が起きやすいから
子供は大人に比べて注意の分散が起きやすいと言われています。例えば、さっきまで忘れないように意識していても、その後に友達に話しかけられたり目に入ったものに注意を向けてしまったりすると忘れてしまうことがあります。特に子供は大人よりも知らないことばかりの世界で生きています。そのため、身の回りで起こることには常に注意を向けてしまうのは自然なのではないでしょうか。
③習慣化することを知らないから
子供にとって自分で意識して習慣化を作ることはとても難しいです。大人でも難しいですよね。どうしたら忘れ物をしなくなるかを工夫するということは大人が教えてあげることで徐々に分かるものです。
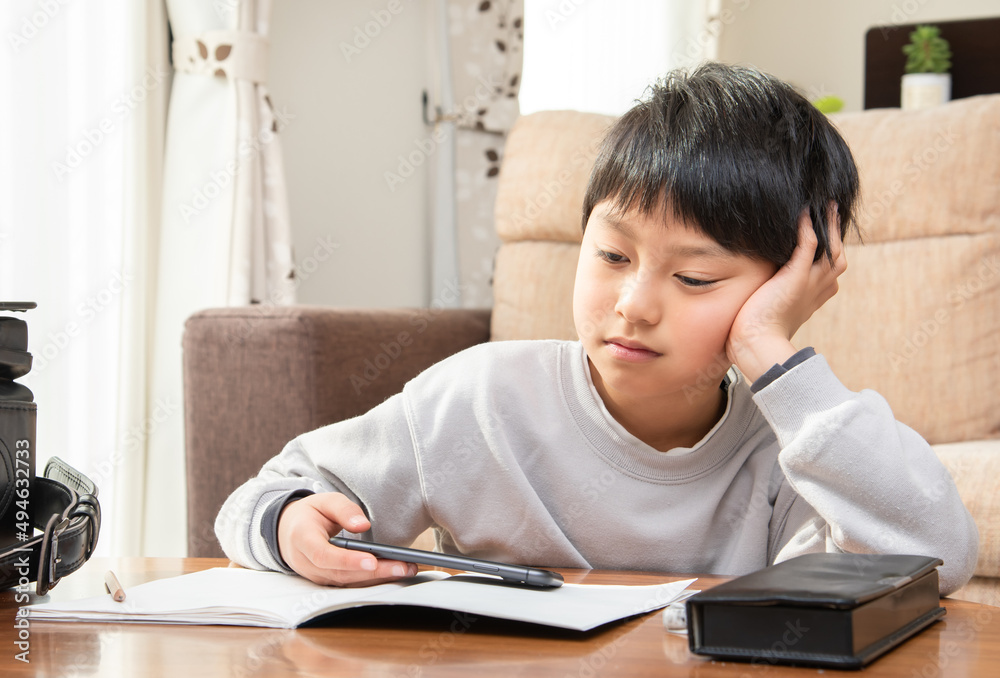
2.忘れ物を減らす3つのサポート法!
①子供の気持ちを理解してあげよう
子供の忘れ物が多いと、思わず叱りたくなるかもしれません。しかし、先述した通り子供はまだ脳や精神が発達段階にあります。なので、子供が忘れ物をしてしまうのは自然なことです。もちろん大人である私たちも子供の頃はたくさん忘れ物をして大人に迷惑をかけてきたと思います。これをしっかり理解して、子供を責めるのではなく、一緒にどう工夫していくか考えてあげましょう!
声がけの例としては
・「忘れ物しちゃったんだね、次は気をつけようね」
・「ここに置いておくと次忘れないかな?」
・「どうしたら忘れないか一緒に考えよう」
など優しく子供に寄り添いましょう!
②子供と一緒に持ち物チェックしよう
学校の日の前日に持ち物のチェックを一緒にしてあげましょう。1人で準備するよりも一緒に1つ1つ確認することで、忘れ物をしづらくなります。また、持ち物のチェックの仕方を子供自身も学ぶことができるため、だんだん1人でも持ち物チェックができるようになります。
お母さん(お父さん)&子供で持ち物チェック
↓
子供が持ち物を確認するやり方を知る
↓
子供自身で習慣化
このような流れを作ることが理想です!
③視覚化して分かりやすく工夫しよう
やはり子供は意識だけでは忘れ物を減らすことが難しい場合があります。そんな時は“視覚化”
しましょう。
例えば、
・明日の準備のチェックリストを壁に貼る
・付箋に書いて見えるところに貼る
・ノートに書いておく
このように視覚化することで例え忘れてしまっても、見てすぐに思い出すことができます!

まとめ
今回は「忘れ物が多い子」にどう接するかというテーマでサポート方法を3つ紹介しました!
お母さん・お父さんだからこそ子供の強いサポーターになることができます!ぜひ今回紹介したサポート方法を今日から実践してみてください!